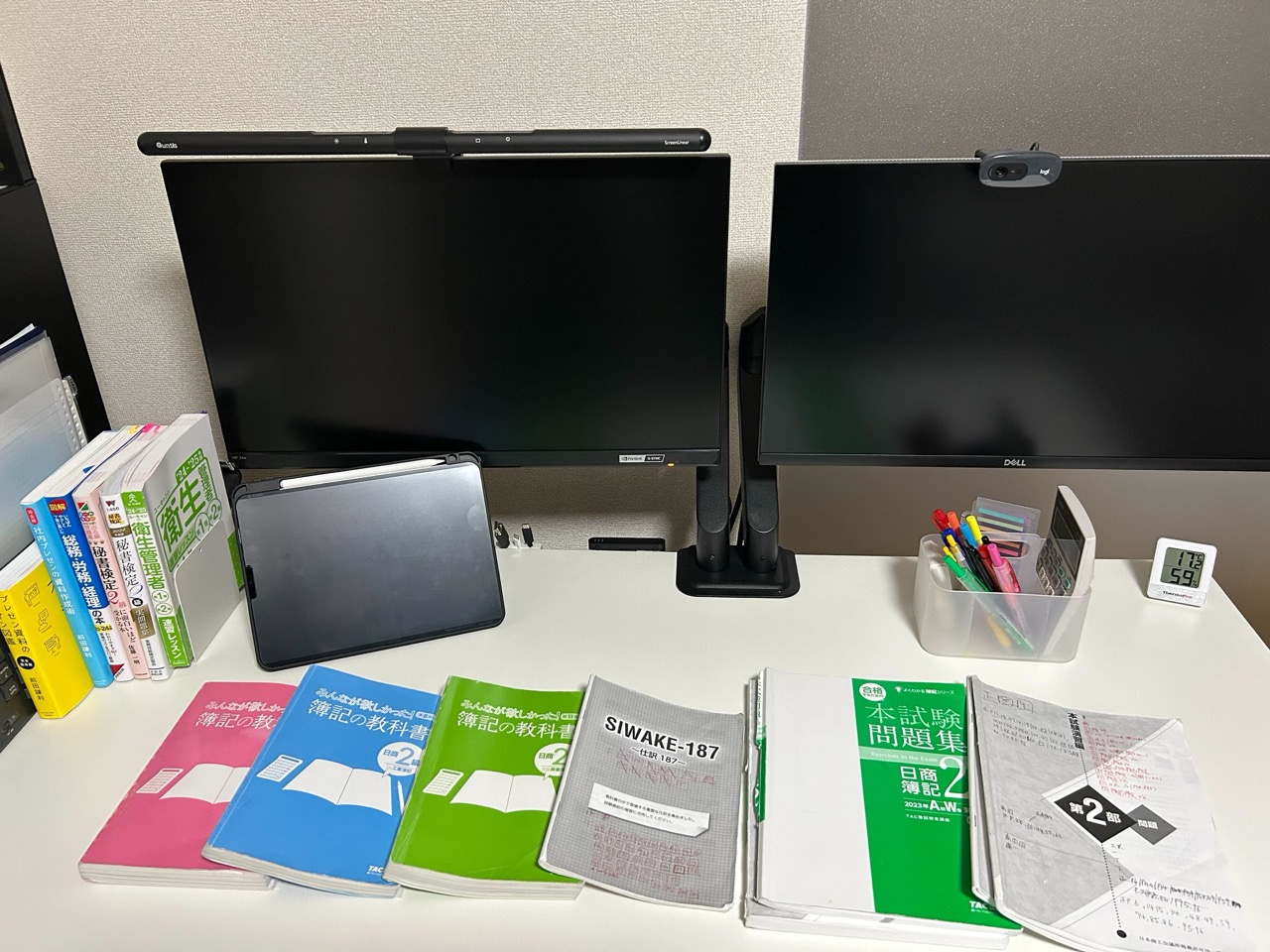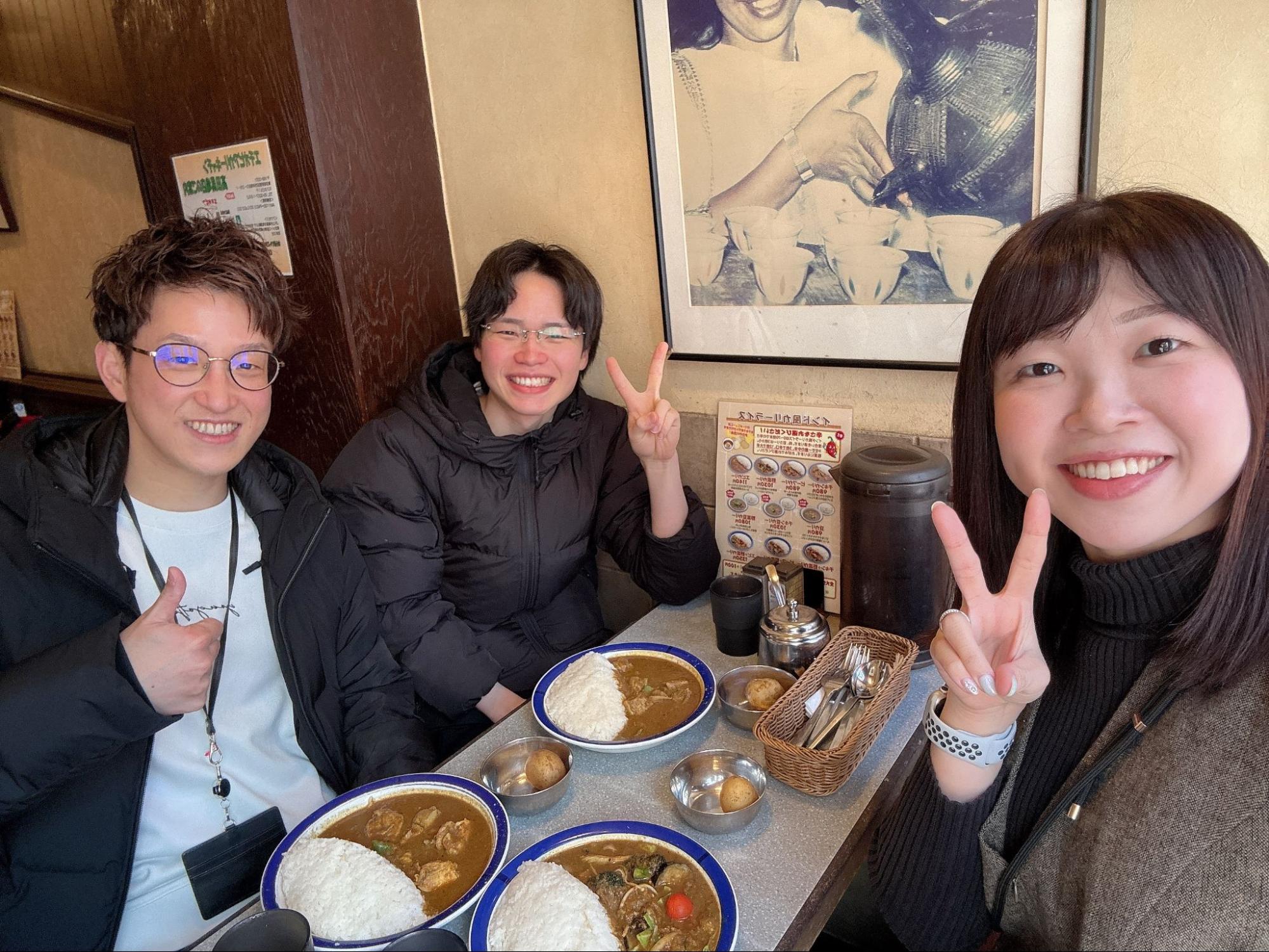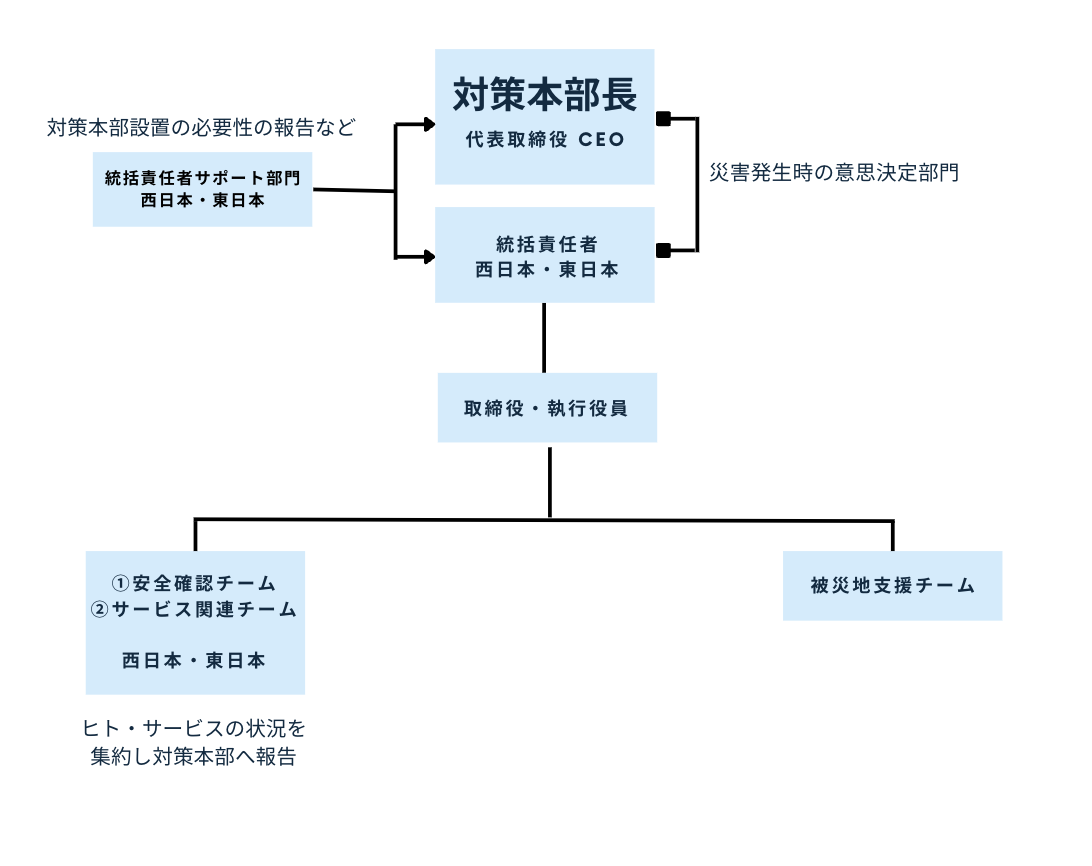経営管理部に所属する山本さん。社員を表彰するアワード、MVV AWARD(※1)にて2024年度のMVPを受賞しました。そんな山本さんに、仕事で意識していることやこれからの目標についてインタビューしました。
※1 i-plugが掲げる5Values、「変化を楽しむ」「全てのステークホルダーに対してフェアである」「創造的な意志を尊重する」「共創しながら価値を出す」「主体的に取り組み、成果創出にこだわる」。MVV AWARDでは、この5Valuesを1年間で最も発揮した社員に贈られる賞です。

株式会社i-plug
山本さん経営管理部
高等専門学校卒業後、ガス会社に入社しサービスエンジニアを担当。2023年5月にアルバイトとしてi-plugに入社し、2023年11月社員に。経営管理部に所属し、総務を担当しながら取締役 COOの秘書も務める。

鹿毛改めて、MVV AWARD MVP受賞おめでとうございます。受賞した時の心境を教えてください。

山本MVPに選出していただき、感謝の気持ちでいっぱいです 。驚きが大きく、今もまだ実感が湧いていません。

鹿毛MVP受賞の山本さんの思いや仕事観について深掘りしていこうと思います。はじめに、現在担当する仕事を教えてください。

山本経営管理部にて総務を担当しています。社内環境の整備や社員のサポートが私の役割です。具体的には、オフィスの維持と改善、備品の管理、社内コミュニケーション施策の実施などをしています。また秘書業務を兼務しており、COOの直木さん(※2)の秘書を担当しています。

鹿毛i-plugへの入社理由を教えてください。

山本私は新卒でガス会社に入社し、メンテナンスを担当するサービスエンジニアとして働いていました。しかし、環境が合わず精神的にまいってしまい、しばらく働くことから離れた時期がありました。
そのようななか、就業支援の会社を通してi-plugを知りました。以前の職種がエンジニアだったため、エンジニア職を中心に探しつつ、人材業界の企業も検討していました。新卒で入社したときに感じた「企業と求職者のミスマッチ」の経験から、そうしたギャップを防ぐ仕事にも興味があったからです。
i-plugを紹介された後、「OfferBox」を知りました。「企業と求職者のミスマッチを減らしたい」という私の思いと、「OfferBox」に込められた思いが共通していると感じ、i-plugに入社したいと感じました。 入社したいと感じた理由は他にもあります。「i-plugでなら新しいことにチャレンジできそう」と思ったからです。働くことや人とのコミュニケーションに対して前向きな気持ちになれない時期もありました。面接前は、過去にとらわれて気持ちが少し後ろ向きになっていました。
しかし、i-plugの面接は想像と全く違うものでした。たとえば、過去を深掘りするのではなく、これからやりたいことに焦点を当ててくれたり、想像以上にフランクな面接官だったりしたのです。「この人たちと働きたい」と感じたことを今でも覚えています。 そして、2023年5月にi-plugの障がい者雇用(※3)枠でアルバイトとして入社し、2023年11月に社員になりました。

鹿毛入社して自身が最も変化したと感じることは何ですか。

山本入社当初は、与えられた業務を確実にこなすことを意識していました。エンジニアからのキャリアチェンジだったことや、働くことに対して前向きな気持ちになれない時期があったこともあり、少しずつ業務に慣れるよう上司と調整。
徐々にできることが増えていくなかで、「社員のみんなのために、もっと何かできることはないか」という気持ちが芽生えました。与えられた業務をこなすだけでなく、「やってほしい」と求められることに対して、「もっと良くしたい」と意識が変わったのです。
今では、自分のやりたいことに対して自ら手を挙げられるようになりました。業務の幅が広がっただけでなく、「もっと社員のみんなのために何かしたい」という意識の変化が、最も大きな変化です。社員がより働きやすい環境を私が作ることで、社員一人ひとりの可能性が広がり、会社の成長につながれば嬉しいと思っています。

鹿毛「もっと社員のみんなのために何かしたい」と思う原動力は何ですか。

山本前職はクレーム対応が多く、オフィス内に重い雰囲気が漂うことがありました。ストレスや小さな不安が積み重なると、人はどうしても心が疲弊して、ピリピリしてしまうものだと思います。そして、ピリピリした雰囲気がきっかけで、人間関係が悪化したり、働くモチベーションが下がったり、悪循環が起きてしまうのです。
i-plugでは、「そのような思いをする人がいない環境であってほしい」という強い気持ちがあります。
なぜなら、i-plugに入社して、これまでとは全く違う、良い環境だと感じたからです。i-plugには、なにごとにもフェアに判断し、真摯に向き合う人たちが多いと思いました。そのような社員たちが「今まで通り、いつもポジティブな気持ちで働ける環境をつくりたい」という思いが、自分にできることを模索する原動力になっています。

鹿毛VP賞受賞において、5Valuesの「すべてのステークホルダーに対してフェアである」を最も体現したと評価されていました。意識していることはありますか?。

山本社員一人ひとりに対して、分け隔てなく、できるだけ同じように接することを心がけています。たとえば、何かを頼まれたときも、個々の状況やニーズを考慮したうえで、各々にとって最適な対応ができるよう意識しています。
また、困りごとを解決するときも同じです。特定の誰かが便利になるのではなく、できる限り多くの社員が、それぞれの立場や状況においてフェアにメリットを享受できる形になっているか考えるようにしています。
以前、CEOの中野さんが「公平(フェア)」と「平等」の違いについて朝会で話していました。その時に「まさに自分が大切にしているのはこれだ」と、腑に落ちた記憶があります。
「平等」は、すべての人に同じものを与えること。 「公平」は、それぞれの状況に応じて、必要なものを適切に提供すること。
私は、後者の「公平」な考え方を大切にしています。
もちろん、いつも完璧にできているわけではありません。私はオフィスに出社することが多いので、よく対面で会う人に意識が向きがちになることもあります。
だからこそ、「フェアな判断ができていたか」を振り返るようにしています。まだ試行錯誤しながらですが、社員のみんなにとってより良い環境をつくるために、何ができるかかを考えて、実行し続けていきたいです。

鹿毛これからの目標を教えてください。

山本i-plugグループのMission「つながりで、人の可能性があふれる社会をつくる」を、i-plugの社内から実現していきたいです。一人ひとりの個性を尊重し、各々が最大限の力を発揮できる環境を作ることが、私の目標です。具体的には、社員が感じる不安や困りごとを解消できるような存在になりたいと思っています 。
「困ったら声かけてください」と待つのではありません。自分からアクションを起こして、相談しやすい関係性を築いていきたいです 。そうすることで、「また何か困ったときは、あの人に聞いてみよう」と思い出してもらえる、安心感のある存在になりたいと思っています。
「ギブアンドテイク」という言葉がありますが、私は見返りを求めずに、まずは自分にできることを惜しみなく「ギブ」し続けることを大切にしています。過程で、社員が活き活きと働き、組織全体がより良い方向へ向かう。
結果として、私自身もその良くなった環境に身を置くことができ、それが私にとっての最大の「テイク」となります。その状況が私の喜びややりがいとなり、さらなる「ギブ」への意欲へと繋がるのです。そういった良い循環が自然と生まれると信じています。これからも私にできることを一つずつ丁寧に取り組んでいきたいです。

鹿毛ありがとうございました。

.jpeg)